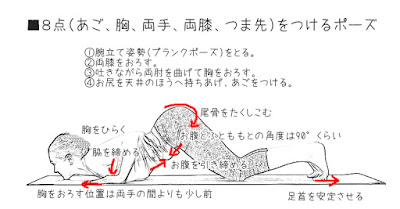■相反抑制テクニック
①罹患した筋肉・原因となる筋肉を同定し、弛緩させる(脱力させる)。
②40%の等尺性抵抗に対して、拮抗筋を収縮させる。
③拮抗筋へのアプローチが相反抑制効果をもたらす。
■等尺性運動後の筋伸張法
①トリガーポイントを同定する。
②罹患した筋肉・原因となる筋肉に対してじゅうぶんな可動域が確認でき、なおかつ苦痛を感じない姿勢にする。
③罹患した筋肉・原因となる筋肉を、最大限痛みのない範囲まで、20%程度の力で収縮する。その間、10秒間等尺性抵抗を加える。筋肉が短くならないように、身体の一部を固定する。
④次に、筋肉を伸張しながら、筋肉が伸びているか、まだ伸びるか確認する。
⑤筋肉を伸張している間は、抵抗があるポイントまで引き伸ばすイメージで、筋肉を徐々に伸ばす(他動)。伸びる筋肉の長さが変化することに気づく。
⑥3回繰り返す。
■コントラクトリラックス・ホールドリラックステクニック
①トリガーポイントを同定する。
②罹患した筋肉・原因となる筋肉に対して、じゅうぶんな可動域が確認でき、苦痛を感じない姿勢にする。
③苦痛がない程度に抵抗を感じる可動域まで硬直した関節を動かし、次に罹患した筋肉・原因となる筋肉を収縮する。
④この自動収縮に徐々に抵抗を加える。
⑤弛緩させる(脱力させる)。
⑥弛緩させることで、関節が動く可動域が増加していく。
■コントラクトリラックス・アンタゴニストコントラクト
①動きの悪い関節や軟部組織、痛みが生じている部位を探す。
②主動筋を収縮させ、その後、主動筋を弛緩させる。
③拮抗筋を収縮させ、主動筋をストレッチする。
④ストレッチは30秒間おこなう。
⑤3回繰り返す。