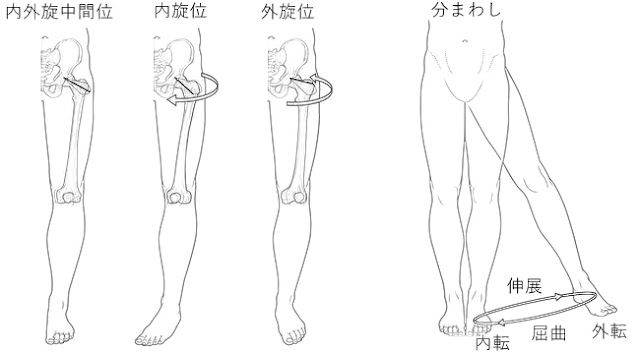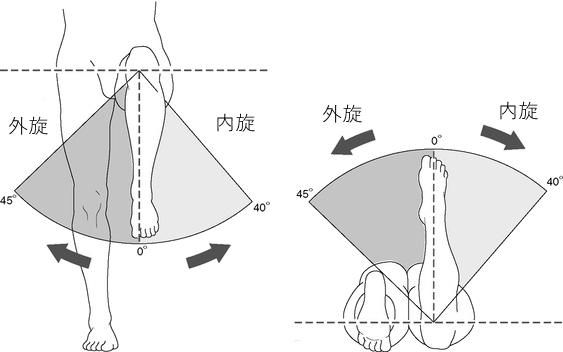|
| 四つん這いで体幹を回旋させるストレッチ(のりこさん・丹ちゃん) |
 |
| ソラシックローテーション(チェストオープナー)(丹ちゃん) |
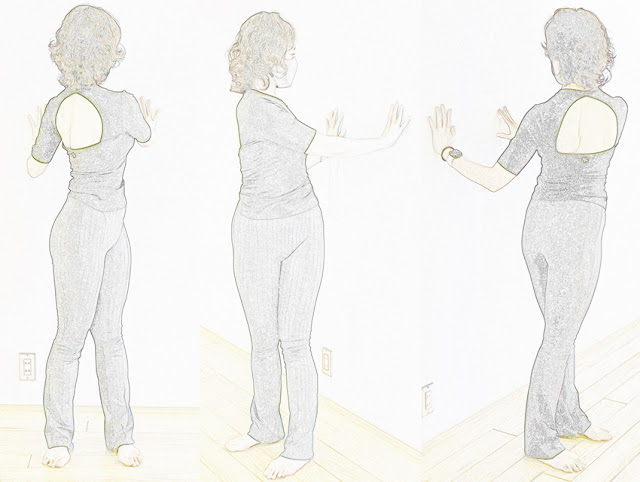 |
| 立位で背中を回旋させるストレッチ |
■回旋筋……横突起から1分節上の棘突起に付着しています。胸椎で最も発達していて、脊柱の真の回旋だけを生じさせます。
 |
| 回旋筋 |
各胸椎の形状とその位置によって脊椎分節が最適に可動し、脊椎における回旋の大部分が胸椎で起こります。
よく、「腰をまわせ」というった誤った動作指導を受けることがあります。腰椎部での長軸回旋範囲はわずか5°です。これに対して、胸椎の長軸回旋運動は35°あります。つまり、長軸回旋運動はほぼ胸椎で行われるのです。「胸をまわせ」「背中をまわせ」という指導がよいかと存じます。
腰椎と腰仙椎移行部は、腰椎屈曲位での過度の回旋、繰り返しの回旋によって損傷しやすいので、脊柱回旋中はあまり動かないようにするべきです。回旋は胸椎から始めます(ウエストから上が動くように意識します)。
腰椎自体の回旋可動域は、胸椎・頸椎に比べ絶対的に小さいということを理解し、腰椎に負担をかけずに身体をコントロールできるよう、胸椎(胸郭)の可動性と、股関節の可動性を高めるようにしていくことが大切です。
胸椎の回旋は、歩行のリズムをつくる要でもあります。
各地のワークショップで解説いたします。
☆大阪ワークショップ
9月23日(木)→ 詳細
☆名古屋ワークショップ
9月24日(金)→ 詳細
☆神戸ワークショップ
9月25日(土)→ 詳細
☆新宮校ワークショップ(平日)
9月26日(月) → 詳細
☆下関ワークショップ
10月1日(日)→ 詳細